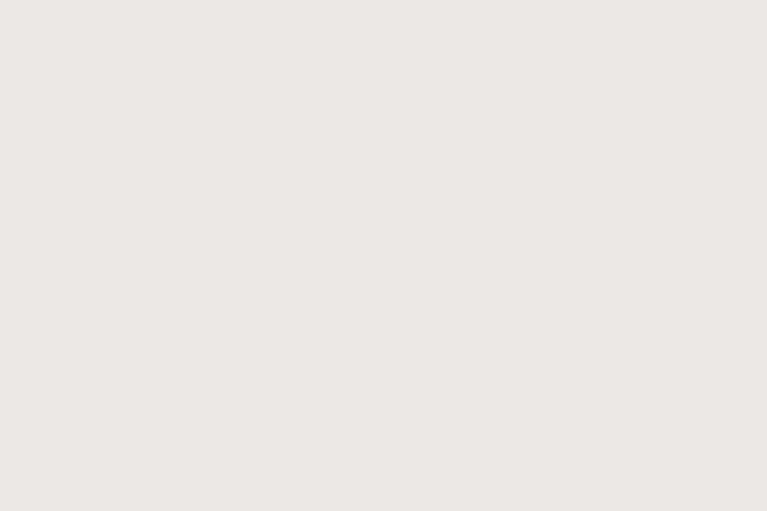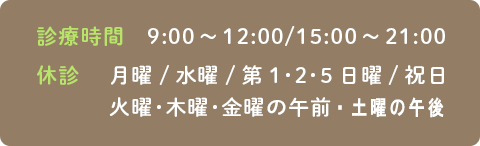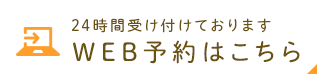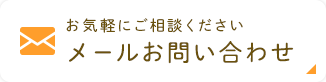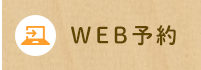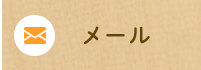矯正歯科の選び方|失敗しにくい7つのポイントと資格の見極め方【保存版】
矯正歯科選びで後悔を減らすために知っておきたい基本

歯並びや噛み合わせの悩みをきっかけに矯正治療を検討する方は少なくありません。ただし、情報が不十分なまま医院を選ぶと、予定より治療が長くなったり、想定と異なる結果になる場合があります。
矯正治療は一般的に1〜3年の期間を要し、通院回数は目安として24〜36回です。費用は自由(自費)診療であり、公的医療保険の適用外です。したがって、クリニック選びは十分な情報に基づいて行うことが重要です。
臨床現場では、転院時に計画の見直しが必要となる事例に出会うこともあります。こうした事態を避けるため、選定時の確認点を把握しておくと安心です。
本記事では、7つの確認ポイントと資格の見方をわかりやすく解説します。これから矯正治療を始める方はもちろん、現在治療中で不安のある方にも役立つ内容です。
矯正歯科と一般歯科・審美歯科の違いを理解しよう
「矯正歯科」「一般歯科」「審美歯科」には役割の違いがあります。
矯正歯科は、歯並びや噛み合わせに関する診断と治療を主に扱い、見た目だけでなく咀嚼や発音など機能面の改善も視野に入れます。
一般歯科はむし歯・歯周病・抜歯など幅広い治療を担い、矯正を扱わない、または限定的に行う場合もあります。
審美歯科はホワイトニングや修復物による見た目の改善を中心とし、歯の移動を伴う矯正とはアプローチが異なります。
矯正治療を検討する際は、矯正の相談・診断体制が整った医療機関で説明を受け、内容を比較検討しましょう。
矯正専門クリニックを選ぶメリット
矯正を主に扱う医療機関では、矯正分野の知識・経験を持つ歯科医師が在籍し、セファログラム(頭部X線規格写真)や口腔内スキャナーなど、診断に資する装置を導入している場合があります。
また、取り扱う症例の範囲が広いこともありますが、他院との数量比較や断定的な優位性の表現は避けるのが適切です。実際の体制や検査内容、説明の分かりやすさを確認し、自分にとって理解しやすい環境かを見ていくと良いでしょう。
失敗しない矯正歯科選びの7つのポイント
矯正歯科を選ぶ際には、以下の7点をチェックしてみてください。これらを押さえることで、判断材料が明確になります。
- 日本矯正歯科学会の資格表示が適切か
医師紹介ページで、**「日本矯正歯科学会 認定医/臨床指導医(旧専門医)」**など、団体名と資格名を併記しているかを確認します。経歴欄での客観的な記載が基本で、希少性や優位性を強調する表現は用いません。
- 説明がわかりやすいか
初回相談で、治療計画・費用・通院回数・治療期間の目安、さらに一般的なリスク・副作用の説明が分かりやすいかを確認します。疑問点をその場で質問できることも大切です。
- 複数の治療法から選べるか
表側ブラケット、リンガル(舌側)ブラケット、マウスピース型(カスタムメイド)矯正装置など、状態・要望・生活環境に合わせた選択肢の提示があり、利点と留意点の双方が説明されているかを見ます。特定の方法のみを一方的に推奨する表現は避けましょう。
- 料金体系が明瞭か
初診・検査・装置・調整・保定などの合計費用の目安や、想定される追加費用の範囲が分かる表示が望まれます。割引やキャンペーン等を強調する見せ方は不当な誘因となるおそれがあるため、料金表で事実を簡潔に示すのが無難です。
- トラブル時のフォロー体制は明確か
装置の破損や痛みなどが起きた際の連絡方法・対応時間帯・担当体制に関する案内があるかを確認します。常勤・非常勤の表記は誤解のない形で行われているかもポイントです。
- 診断・治療に関わる設備の案内が具体的か
セファログラムやデジタルX線など、診断や治療に資する機器の有無が具体的に示されていると比較検討しやすくなります。利点のみを強調せず、検査に伴う不快感や被曝への配慮なども併記されているとより適切です。
- 通いやすさ(アクセス・診療時間)
月1回程度の受診が1〜3年続くのが一般的です。アクセス性、診療時間、予約方法など、通院継続のしやすさも判断材料に含めましょう。

矯正歯科医の資格と専門性を見極めるポイント
ウェブ掲載では、資格名と認定団体名を併記し、経歴欄に客観的に記載するのが基本です。**「矯正専門医」の表現は誤認の恐れがあるため、「矯正歯科治療を主に行う歯科医師」**のように分かりやすく伝えると適切です。資格の希少性を示す割合表示や、優位性の強調は用いません。
矯正歯科の看板の見方
診療科目の列挙だけでは専門性を判断できません。ウェブ上では、診療内容・検査・費用・治療期間と通院回数・一般的なリスク/副作用などをわかりやすく提示することが大切で、煽る表現や体験談の掲載は避けます。
矯正専門医院と一般歯科での矯正の違い
担当体制(常勤/非常勤)や診断装置の導入状況は医院により異なります。担当変更の可能性や診療日が誤解のないよう案内されているかを確認しましょう。症例数や「最先端」「最良」などの優位性を示す表現は広告上不適切となるため用いません。
矯正治療の失敗例と避けるべきポイント
噛み合わせの改善不足、正中のずれ、顎の不快症状、歯根吸収、治療期間の長期化などの課題が生じる場合があります。
回避のためには、パノラマやセファログラム等に基づく計画、担当体制の明確化、症例の提示方法と留意点の説明を確認します。ビフォーアフターを示す際は、主訴・診断名(主症状)・年齢・主な装置・抜歯部位・治療期間・費用概算・個別のリスク/副作用の8項目を同一画面で併記するのが適切です。
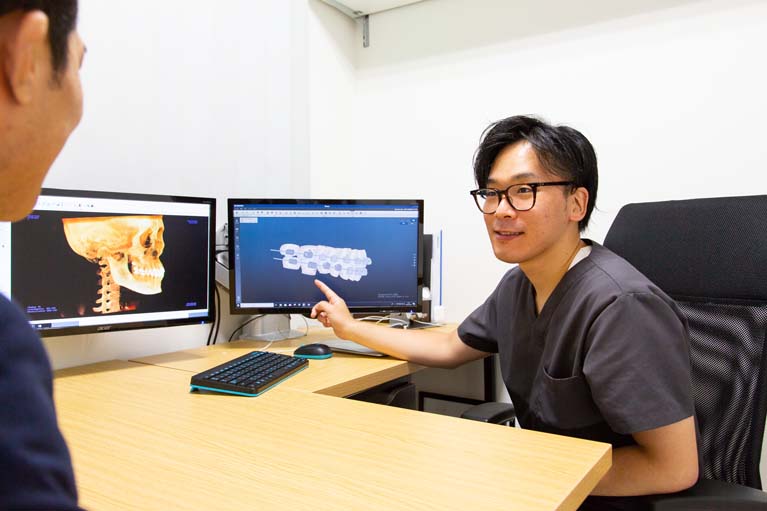
矯正歯科での初診相談で確認すべきこと
初診相談では、現在の状態・治療選択肢(利点と留意点)・治療期間の目安・通院回数・費用内訳・一般的なリスク/副作用・担当体制を質問します。判断に迷う場合はセカンドオピニオンの活用も一案です。費用の案内については、料金表ページで自由診療である旨と治療期間1〜3年/通院回数24〜36回の目安をあわせて確認できると分かりやすくなります。
まとめ:失敗しない矯正歯科選びのポイント
矯正治療は自由(自費)診療で、一般に1〜3年、24〜36回程度の通院が目安です。だからこそ、資格表示の適切さ、説明の分かりやすさ、複数選択肢の提示、料金表示の明瞭さ、対応体制、設備とその役割の明示、通院しやすさを総合的に確認することが重要です。
初診相談では遠慮せずに質問し、不安や疑問を解消したうえで計画を検討しましょう。一般的なリスク・副作用(疼痛・不快感、歯根吸収、歯肉退縮、むし歯・歯周病のリスク増、装置破損や再装着、発音・咀嚼への一時的影響、保定期の後戻り等)にも留意し、症例ごとの説明を受けてください。
大阪市北区の医療機関情報や診療時間等を記載する際は、事実に基づく客観的な案内に留め、無料・割引の強調、比較優良/誇大な表現は避けるよう運用してください(費用や相談の取扱いは料金表内で簡潔に記載すると適切です)。
詳細はみなみもりまちN矯正歯科のホームページをご覧ください。あなたに合った最適な矯正治療プランをご提案いたします。
著者情報
院長 農端 健輔

経歴
2007年大阪歯科大学 卒業
2012年大阪歯科大学大学院私学研究科博士課程修了
2012年大阪歯科大学歯科矯正学講座において助教として勤務
2016年日本矯正歯科学会 認定医取得
2017年みなみもりまちN矯正歯科 開設
所属団体
近畿東海矯正歯科学会
日本矯正歯科学会
日本顎変形症学会
日本口蓋裂学会
World Federation of Orthodontists